教員・卒業論文紹介Professors & Graduation thesis
あなたの知的好奇心に応える、心理学のエキスパート
武藤 崇 教授

| 専門領域 | 臨床言語心理学、生老病死を考える心理学 |
|---|---|
| 担当科目 | 公認心理師の職責、福祉心理学、バリアフリーの心理学特論 など |
| 現在の研究テーマ |
|
| 私にとって心理学とは | 社会と自分とを再帰的に繋いでくれる「器官」 |
| メールアドレス | 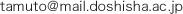 |
Message
心理学は「生きる力」を科学的に援助する学でもあります。それを体現する「サイエンティスト・プラクティショナー(科学者でもあり実践家でもある人)」になろうという「志」をもった人が集ってくれることを願っています。
研究紹介
ことばとの「うまい」つきあい方がメンタルヘルスの鍵になる
メンタルヘルスは「ことばとのつきあい方・使い方」で良くも悪くもなることが、近年の臨床心理学の研究で明確にされつつあります。しかし、わたしたちは、学校教育(国語など)のなかで、その「つきあい方・使い方」を直接教わる機会がありません。それに関する研究を進展させ、最新知見を普及・実装させて、さらに生活の質(QOL)の向上を目指していきます。

※「認知行動療法」「臨床心理学」が気になる方は、下記教員ページもご覧ください。
ゼミ紹介
ことばのもつ影響力を見極め
メンタルヘルスに役立つ新たな方法を開発する。
行動分析学(臨床行動分析)の専門家であり、公認心理師/臨床心理士でもある武藤先生。人間の心理・社会的な問題(深層心理も含め)を「行動と環境との相互作用」の観点から捉え直し、新たな問題解決の開発やウェルビーイングの拡大のために、日々研究や実践をされています。
ゼミでは、学生の日常的な問題意識を行動分析学的に検討し、ユニークな発想を創出するように取り組んでいます。とくに、人間が自分の器官のように使っている「ことば」に焦点を当て、それが持っている影響力(そのダークサイドも含め)について研究を行っています。

論文テーマ例
卒業論文
- 価値の明確化がライフスキルに及ぼす影響の検討
- 心理的ウェルビーイングは価値の明確化で向上するのはなぜか
- 価値についての対話が,価値の明確化に及ぼす影響
修士論文
- 身体醜形懸念を有する女子大学生に対するアクセプタンス&コミットメント・セラピーの効果の検討
- 心理的ウェルビーイングの向上を目的とした 価値の明確化とコミットされた行為に焦点を当てた アプローチに関する検討
博士論文
- 抑うつ的反すうに対する脱フュージョン手続きの効果:効果測定法の開発とその妥当性の検討(2017年度)
- 価値の明確化が慢性疼痛患者の行動活性化に及ぼす影響の検討(2016年度)
- 肥満者の行動的QOLの拡大と生活習慣セルフマネジメントにおける行動変動性の機能とその応用(2014年度)
- アクセプタンス&コミットメント・セラピーの治療文脈の確立:Creative Hopelessnessの促進方法の効果検証(2013年度)
- 不安障害に対する脱フュージョンの効果:作用メカニズムと効果測定法の検討(2012年度)

